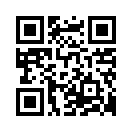2021年01月22日
「『国民一斉検査』を前提とした準備は不可能」との報道
絶対に不可能です。
報道は、こちらです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/a1dce94cdaefc3101bd34dc30f3d60e12b0033a2?page=3
(以下は、コピーです)
検査は「医師が必要だと判断した症例に対して」行う
厚生労働省のウェブサイトによると、国内におけるPCR検査の1日あたりの最大能力は12万1769件(1月5日時点)。日本の人口1億2571万人(総務省統計局資料より。20年12月1日現在の概算値)全員が受けるとすると、仮に毎日最大件数を実施できたとしても、単純計算で1000日以上、約3年かかる。
PCR検査の1日あたり実施件数は、20年6月まで1万件に満たない程度だったが、徐々に拡大している。ただ、増えたとはいえ12月には1日あたり多い時で6万件程度。また、現在の感染の有無を調べるには、PCR検査のほかに抗原検査があるが、こちらも12月下旬時点で1日あたり1万3000件ほど。
同省が公表している20年12月30日時点の「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、病床数等に関する調査結果」によると、確保病床数は全国合計で2万7515床、入院者数は1万1585人。宿泊療養所の確保居室数は同2万6679室、宿泊療養者数は5562人となっている。
舘田氏はさらなる問題として、「検査を続ければ偽陽性や偽陰性が一定数出ます。コスト面でも、安くなっても1回数千円かかります。国民全員が検査し続けるために、お金を出し続けるのか。意味がない」と指摘。「それ(一斉検査)よりも、すべての人が感染している可能性、感染させてしまう可能性があると考え、適切にマスクをし、手洗い、消毒を徹底し、濃厚接触をやめること、『3密』を避けること、ユニバーサル・プレコーション(すべての人に感染性があるものとして対応する考え方)です」と話した。
PCR検査は「医師が必要だと判断した症例に対して、保険診療点数をつけて行う」という考えは変わらない。加えて舘田氏は「不安だから検査したいという人もいますので、その場合は街角検査(民間検査)を自費で受けてもらう。ただし大事なのは、街角検査にしてもクオリティ・コントロールが保証できることと、陽性だった場合は医療機関にかかり、適切な指示を受けながら、本当に新型コロナウイルス感染症かどうかを必要に応じてもう一度検査することです」としている。
「『国民一斉検査』を前提とした準備は不可能だったと思われます」
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科の山岡昇司教授(ウイルス制御学)は8日、取材に対し、コストやメリットなどを考える以前の問題があるとする。「『国民一斉検査』は非現実的であり、それに限られた予算と人的資源を使うより、他にすべきことがあると考えます」とし、理由として(1)現検査能力では時間がかかりすぎる(2)検査時点での陰性はその後の非感染を意味しない(3)医療・宿泊施設の現収容能力では、陽性者への対応ができない(4)今後重要なのは、死者を減らすことである――の4点をあげた。
(1)は、「COVID-19の流行についてはこれまで、経済との綱引きの中で様々な意見が出され、その中には楽観的見通しもあったことは事実で、検査体制も医療体制もまさかの事態に備えるよう整備されてきたとは言えません。そもそも、第1波、第2波の際に第3波の規模を誰がどこまで正確に予見しえたか? そのような状況下で、『国民一斉検査』を前提とした準備は不可能だったと思われます。検査能力をさらに拡充すべきであることは明白ですが、検査能力とともに医療体制も拡充しなければ意味がない」という。
(2)はやはり、「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)の感染伝播効率が非常に高いことを考えれば、『国民一斉検査』は仮に実現したとしても『ある時点での調査』くらいの意味合いしかないでしょう」と、有効性に疑問を示した。
(3)の医療機関や宿泊施設の収容力については、「COVID-19は『2類感染症相当』という枠組みがいまだに存在し、民間病院が8割近くを占める日本の現状で、公的医療機関、保健所の業務が破綻しつつあります。1日7000人近くの新規感染者数は深刻な数字ですが、現検査体制下でこれはおそらく氷山の一角にすぎず、実際の新規感染者数はこれよりはるかに多いでしょう」としたうえで、「仮に『国民一斉検査』を実施できたとしても、その結果を引き受ける医療体制が今の日本にはありません」と、受け入れ能力に限界があることを指摘した。
そして(4)の「死者を減らす方法」は3つ。「特効薬と有効なワクチンの開発、医療体制の整備です。特効薬ができない限り、死者を減らすためには感染者を減らさなければならず、そのためには有効なワクチンの接種が必要です。COVID-19重症者を救うだけでなく、他の生死にかかわる疾患についての医療水準を維持することも喫緊の課題です」との見解を示した。
報道は、こちらです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/a1dce94cdaefc3101bd34dc30f3d60e12b0033a2?page=3
(以下は、コピーです)
検査は「医師が必要だと判断した症例に対して」行う
厚生労働省のウェブサイトによると、国内におけるPCR検査の1日あたりの最大能力は12万1769件(1月5日時点)。日本の人口1億2571万人(総務省統計局資料より。20年12月1日現在の概算値)全員が受けるとすると、仮に毎日最大件数を実施できたとしても、単純計算で1000日以上、約3年かかる。
PCR検査の1日あたり実施件数は、20年6月まで1万件に満たない程度だったが、徐々に拡大している。ただ、増えたとはいえ12月には1日あたり多い時で6万件程度。また、現在の感染の有無を調べるには、PCR検査のほかに抗原検査があるが、こちらも12月下旬時点で1日あたり1万3000件ほど。
同省が公表している20年12月30日時点の「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、病床数等に関する調査結果」によると、確保病床数は全国合計で2万7515床、入院者数は1万1585人。宿泊療養所の確保居室数は同2万6679室、宿泊療養者数は5562人となっている。
舘田氏はさらなる問題として、「検査を続ければ偽陽性や偽陰性が一定数出ます。コスト面でも、安くなっても1回数千円かかります。国民全員が検査し続けるために、お金を出し続けるのか。意味がない」と指摘。「それ(一斉検査)よりも、すべての人が感染している可能性、感染させてしまう可能性があると考え、適切にマスクをし、手洗い、消毒を徹底し、濃厚接触をやめること、『3密』を避けること、ユニバーサル・プレコーション(すべての人に感染性があるものとして対応する考え方)です」と話した。
PCR検査は「医師が必要だと判断した症例に対して、保険診療点数をつけて行う」という考えは変わらない。加えて舘田氏は「不安だから検査したいという人もいますので、その場合は街角検査(民間検査)を自費で受けてもらう。ただし大事なのは、街角検査にしてもクオリティ・コントロールが保証できることと、陽性だった場合は医療機関にかかり、適切な指示を受けながら、本当に新型コロナウイルス感染症かどうかを必要に応じてもう一度検査することです」としている。
「『国民一斉検査』を前提とした準備は不可能だったと思われます」
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科の山岡昇司教授(ウイルス制御学)は8日、取材に対し、コストやメリットなどを考える以前の問題があるとする。「『国民一斉検査』は非現実的であり、それに限られた予算と人的資源を使うより、他にすべきことがあると考えます」とし、理由として(1)現検査能力では時間がかかりすぎる(2)検査時点での陰性はその後の非感染を意味しない(3)医療・宿泊施設の現収容能力では、陽性者への対応ができない(4)今後重要なのは、死者を減らすことである――の4点をあげた。
(1)は、「COVID-19の流行についてはこれまで、経済との綱引きの中で様々な意見が出され、その中には楽観的見通しもあったことは事実で、検査体制も医療体制もまさかの事態に備えるよう整備されてきたとは言えません。そもそも、第1波、第2波の際に第3波の規模を誰がどこまで正確に予見しえたか? そのような状況下で、『国民一斉検査』を前提とした準備は不可能だったと思われます。検査能力をさらに拡充すべきであることは明白ですが、検査能力とともに医療体制も拡充しなければ意味がない」という。
(2)はやはり、「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)の感染伝播効率が非常に高いことを考えれば、『国民一斉検査』は仮に実現したとしても『ある時点での調査』くらいの意味合いしかないでしょう」と、有効性に疑問を示した。
(3)の医療機関や宿泊施設の収容力については、「COVID-19は『2類感染症相当』という枠組みがいまだに存在し、民間病院が8割近くを占める日本の現状で、公的医療機関、保健所の業務が破綻しつつあります。1日7000人近くの新規感染者数は深刻な数字ですが、現検査体制下でこれはおそらく氷山の一角にすぎず、実際の新規感染者数はこれよりはるかに多いでしょう」としたうえで、「仮に『国民一斉検査』を実施できたとしても、その結果を引き受ける医療体制が今の日本にはありません」と、受け入れ能力に限界があることを指摘した。
そして(4)の「死者を減らす方法」は3つ。「特効薬と有効なワクチンの開発、医療体制の整備です。特効薬ができない限り、死者を減らすためには感染者を減らさなければならず、そのためには有効なワクチンの接種が必要です。COVID-19重症者を救うだけでなく、他の生死にかかわる疾患についての医療水準を維持することも喫緊の課題です」との見解を示した。
Posted by いざぁりん
at 00:07